記事詳細
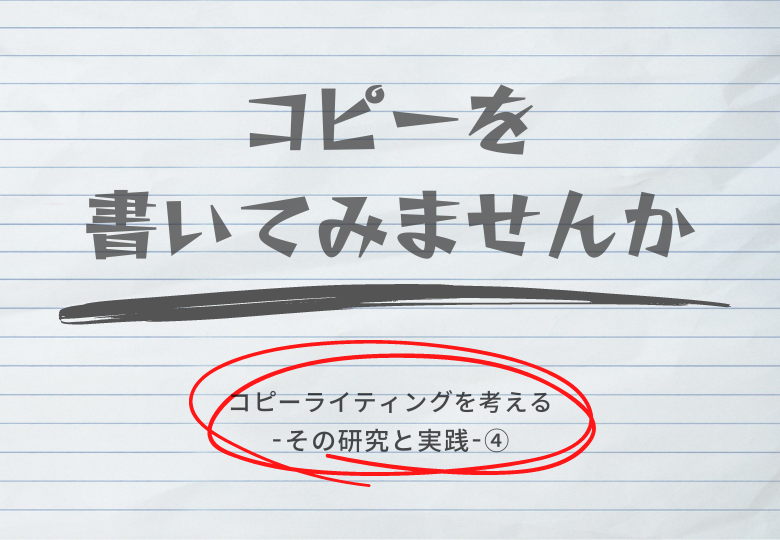
第四回 コピーを書いてみませんか

三島邦彦
今回は、コピーを書くということについて考えてみます。
コピーを書くとは何を書くということなのか。
どういう行為なのかを考えてみようと思います。
これからコピーを書くということを説明していくにあたって
いきなりこんなことを言うのもなんですが、
まず大事なことは、コピーを書くことを特別なことにしない、
ということのような気もしています。
コピーというものを特別視しない。コピーはただの言葉である。
そんなクールな視点がコピーを書くということには必要です。
書けるとか書けないとかではなく、とりあえず書くことの大事さ。
コピーが好きであることは大事なのですが、コピーを特別視することはやや危険なところがあるのでその違いに慎重でありたいと思います。
若い人が書くコピーには、力みや不安が感じられるものが多くあります。その力みや不安をなくしていくことがコピーを書けるようになるということなのかもしれません。コピーを勉強することの最終的な目標は、コピーを特別視しなくなること。フラットな心で、その時々の課題に向き合い書くために。
コピーに限らず、不安な場合、人は定型に頼りがちです。コピーを書くときも、コピーっぽい言い回しに頼ってしまいます。どこかでこういうコピーがあったような気がするもの。それはスタート地点であって、ゴールではない。定型から抜け出し、あなたのコピーを書くために、コピーについて考えはじめましょう。
それは文学ではない
コピーを考えるにあたって、文学との違いからはじめてみます。小説、戯曲、短歌、俳句、文学にはいろんな形式があります。そして、これら文学とコピーは大きく違う。
古来、さまざまな作家によって書かれた広告文があります。そしていくつかの例外を除いて、どれもあまりうまくいっているとは思えない。その作家の本来の味わいが表現されているものにはなりえていない。もちろん、開口健や山口瞳をはじめ、現代でも伊集院静さんなど、広告業界を経て作家になった人たちはもともとの広告技術があるのでさすがに上手いのですが、そうではない作家が広告文を書くと途端によくなくなってしまう。そんな現象がなぜ起きるのか。
文学とコピーの違いを一般的な図式で表現すると、
文学はB to C
コピーはB to B to C
という形で説明できます。コピーとは、C(=生活者)への効果を期待されてB(=クライアント)に買われる言葉です。
この違いが、作家とコピーライターの違いにおいて決定的な意味を持っている。
もちろん、出版というビジネスにおいても出版社の編集者というある意味でのクライアントが存在するわけですが、商品はあくまでも作家の言葉、ひいては作家自身なわけです。
一方で、コピーライターが書く言葉は、あくまでクライアントの企業の言葉、商品の言葉です。この企業が今これを言うことに意味がある。この商品だからこそこんなことを言う意味がある。独立した言葉ではなく、企業や商品との掛け合わせ。そこにこそコピーの面白みがある。自分自身ではなくクライアントの言葉として、言葉の価値を考えるのがコピーライターです。
社会人になりたての頃、会社の同期に誘われて参加した多業種の勉強会でコンサルティングファームの人が言っていた「法人もまた人である」という言葉がとても印象に残り、企業の人格をとらえて、ふさわしい言葉を考えるのがコピーを書くことだと思うようになりました。コピーは単体で成立するものではなく、企業ロゴや商品名とセットになって完成する。そこに単なる足し算ではなく掛け算の効果が生まれるかどうかが、コピーの力でありコピーライターの力なのだと思います。
洞察と表現と説得、この3つの力がコピーには必要だと以前書きました。説得の有無というのが文学との大きな違いかもしれません。洞察というのも、文学においては重要ではないかもしれません。
課題を洞察し、クライアントを説得し、それを読もうと思っていない人のために世に出る言葉。言葉を使った特殊な技芸ではあるけれど、決して文学ではない。そして実は、そこにこそ広告のおもしみがあるんじゃないかなと、僕は思ったりしています。
この記事は
ADBOXプラン会員限定コンテンツです。
残り5,656文字
![コピーライター向けオンライン広告講座のADBOX[アドボックス]](/assets/images/common/logo_hrader.svg)







