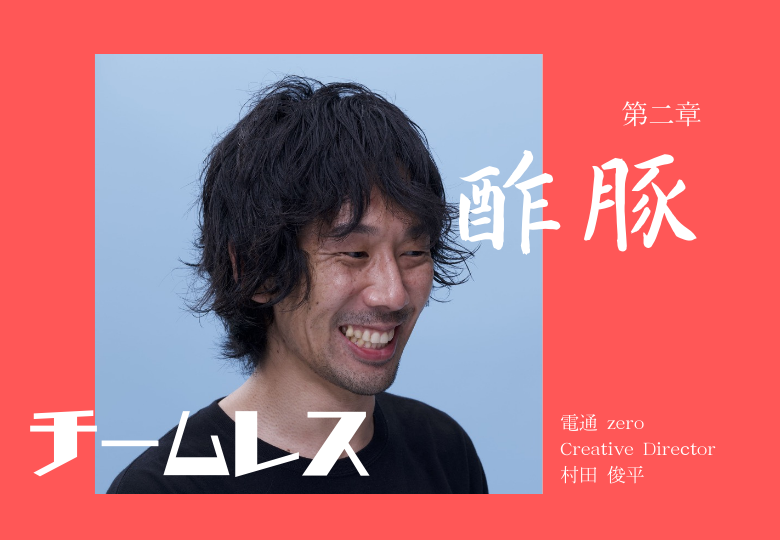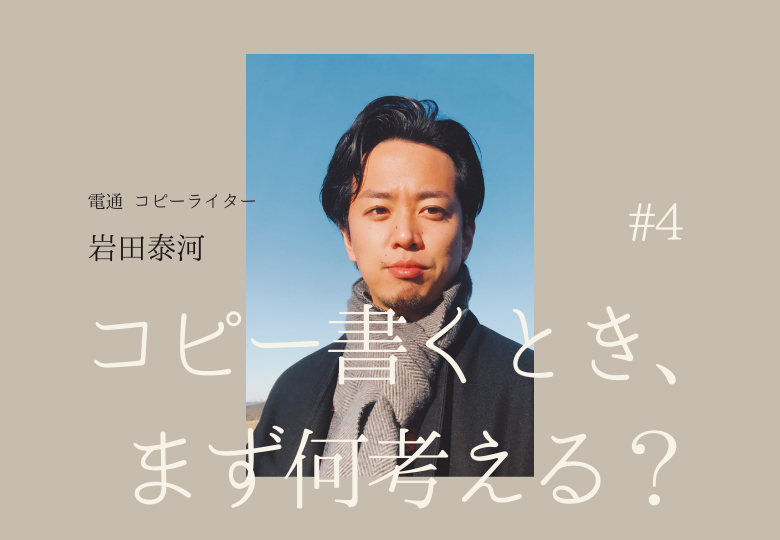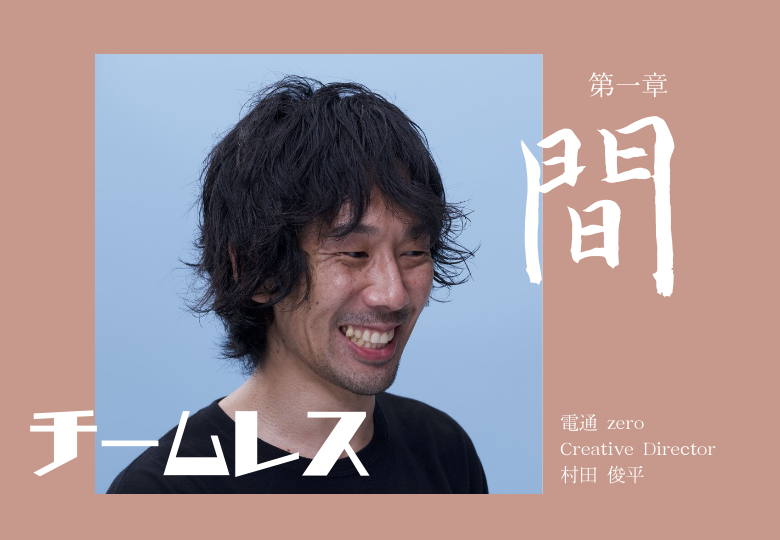記事詳細
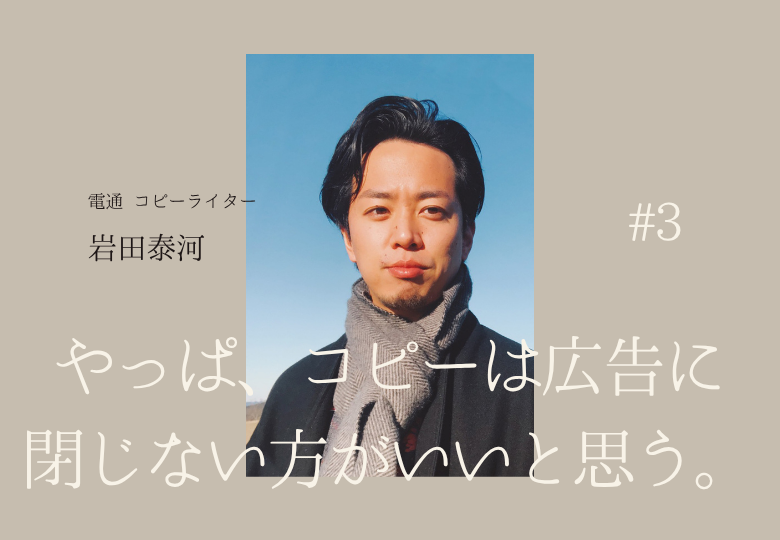
やっぱ、コピーは広告に閉じない方がいいと思う。

岩田泰河
電通でコピーライターをしている岩田泰河です。
2014年入社で、現在、12年目になります。
コピーライターなので、コピーについて書きます。
自分が脳内で最近考えている、
かなりマニアックかつハードコアなことを垂れ流します。
コピーにモヤっている
最近、ずっと考えています。
「コピーってどのくらい嫌われてるんだろう」
「いや、そもそも嫌われるほどの存在感も、もうないんじゃないだろうか」
「とはいえ、コピーはどこまで変わっていくといいんだろう」とか。
大きな前提として、現代人が目にする文字が10,20年前と比べて急激に変わっている、
というのがあって、
それに対してコピーの変化が追いついていない、という感覚があります。
そして、その感覚をどうにかしないといけないな、というモヤモヤがあります。
コピーは時代によって変わるものだとすると、
時代とコピーのざっくりとした変化を、コピー史として振り返ってみたいと思います。
いろんなトレンドはありますが、文語、口語、SNS語、という3つの流れで見てみます。
時代とコピー
①文語の時代
1990年代くらいまではコピーの多くは文語がベースにあったと思います。
本を読む人も多かったので、「です」「ます」「である」調が中心だったり、
2025年現在の感覚からするとかなり文学的なレトリックが多かった印象もあります。
口語っぽいコピーがあったとしても、
「おい〇〇」とか「〇〇だなあ」「〇〇してごらん」みたいな、情緒的な空気が漂います。
仲畑貴志さんの「おしりだって、洗ってほしい。」も、
力は抜けているものの「おしり」とか「ほしい」とか、
どことなく上品な感じが残っていますよね。
②口語の時代
1990年代半ばから2000年代は、もうちょっとくだけてきて、口語のコピーも増えてきた印象。
佐藤雅彦さんのような語感とリズムがおもしろいコピーが受け入れられたり、
タグボートが若者言葉を多用して一気に読後感を軽くしたり、
澤本嘉光さんのコンテのような高速な掛け合いセリフがそのままコピーとして機能したり、
コピーの世界が大きく広がった感覚があります。
お茶の間にあるテレビという強烈なオーディオ媒体
(あえて、映像媒体ではなくオーディオ媒体と言っています)
の強みを活かして、「文語じゃなくて口語で伝えたほうが効率もいいしおもしろいね」
となったのではないでしょうか。
「そこは持っとかないと。」「行っちゃった方が早いんじゃないの?」「伝わってる?」など、
言いたくなるような口語的なコピー、個人的には大好きです。
「そうだ京都、行こう。」は、口語をうまく使って成功した代表的なコピーかもしれません。
CMプランナーが発想したコピーって感じがして、今見ても爽やかで新しい印象です。
③SNS語の時代
問題は、2010年代、2020年代のことばです。
やっぱりSNSの影響による日本人の言語環境の変化は無視できません。
本を読む人もさらに減って、スマホでSNSにつぶやかれる文字を見ることのほうが多いのではないでしょうか?
リアルで日常的なことばが溢れるようになって、ことばのトレンドも早くなりました。
動画でも、テレビ的に編集されたことばではなく、もっとむき出しの表現や言い回しが増えている印象。
ちなみに、いま「リアル」と書きましたが、
特に2020年以降のSNSではアルゴリズムで拡散されやすいことばが中心になっているので、
必ずしもリアルではないことばが拡散されていると個人的には思っています。
イメージ的には「〇〇すぎてやばい」という表現に代表されるように、
感情を煽るために刺激強めの味付けがされていることばたち。
これは日常会話で使うと恥ずかしい感じのことばが多かったり、
現実を誇張していたりするので、
あえて口語ではなく「SNS語」として理解しています。
難しいのが、SNS語には短期的なミーム・内輪ノリ的な面も多いところで、
SNSでバズっているからといって広告にそのまま転用すると、逆に嘘っぽかったり、
広告が出る頃には消費されていてスベったりするところです。
知らない人には知らない言い回しだったりもするので、
ターゲットが多様な広告には使いづらいという面もあります(逆に言えば、特定のトライブでは機能しやすい)。
で、このSNS語や、SNS的なバイブスをちょうどよく入れたことばが、
まだ広告界にコピーとしてうまく定着できていないという感覚がずっとあり、
それが冒頭のモヤモヤにつながっています。
マンガやアニメなどの強いカルチャーが大量に流れ込み、日々すごいスピードでことばが流行り廃り・・・
というタイムラインの中で、広告という様々な制約を背負った条件から生まれることばは
あまりにも無力に感じ、いろんなモヤモヤが生まれます。
文語が死にかけているとすると、どのくらい口語にするのか。SNS語っぽくするのか。いやでもSNSに寄っていくと、それはタイムラインに流れることばと同化するのではないか。グラフィックにSNS語を入れると目立つけど、それがバズってSNSのタイムラインに流れたとき、逆に「ふつう」に感じるのではないか。どのくらい、「コピーっぽくなく」すればいいのか・・・。
「コピーっぽさ」
この「コピーっぽさ」とこの半年くらい向き合っています。
コピーって、いつの間にこんなに人気がなく、嫌われる感じになっちゃってるのか。
コピーの話を離れて、一回、広告に戻ります。
この記事は
ADBOXプラン会員限定コンテンツです。
残り3,874文字
![コピーライター向けオンライン広告講座のADBOX[アドボックス]](/assets/images/common/logo_hrader.svg)